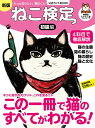猫検定の合格率って実際どれくらいなんだろう?
何割取れたら合格できるのか不安…

猫好きの間でじわじわと注目を集めている「猫検定」。本記事では、猫検定の合格率に関する最新情報を中心に、合格の目安や試験の傾向について詳しく紹介していきます。
「猫検定は何割で合格?」と気になって検索してきた方も多いかもしれません。実は、ねこ検定の初級の合格率は80%前後とされており、他の級に比べて比較的合格しやすいと言われています。
とはいえ、出題内容は広範囲にわたり、初級問題の傾向をしっかり把握しておく必要があります。
また、「猫検定は国家資格?」といった疑問を持つ方のために、資格の位置づけや、合格することで得られる特典についても触れていきます。
猫検定に合格すると、どんなメリットがあるのかを明確に理解できる内容です。
これからの受験を検討している方に向けては、「猫検定の合格率 2024」の変化や、猫検定2025の試験日程にも言及します。勉強時間の目安や、学習のコツ、公式テキストの活用法も取り上げますので、初めての方でも安心して試験対策を始められるでしょう。
さらに、過去問の活用法や、猫検定のオンライン試験はカンニングできるのでは?に関する実態など、ネットで多くの人が気にしているリアルな情報も掲載。本記事を読むことで、猫検定に関する基本的な疑問が一気に解決できます。
これから猫検定を受けてみたい方はもちろん、どの級からチャレンジするか悩んでいる方にとっても、役立つ情報を盛り込んだ内容になっています。
猫検定の合格率はどれくらい?

- ねこ検定初級の合格率は?
- 猫検定の合格率2024の最新データ
- 何割で合格できる?
- 猫検定2025年はいつ?
- 猫検定の合格率と難易度の関係
ねこ検定初級の合格率は?
ねこ検定の合格率(2025年第8回分) 初級:去年よりアップの82.3% 中級:去年より大幅アップの65.7% 上級:過去最高の59.6% 中級上級は平均点も過去最高でラッキー回だったかも 次回は2026年3月22日(日)開催予定 チャレンジしてみて😺 #ねこ検定合格率
ねこ検定初級の合格率は、2023年のデータによると82.7%と非常に高い水準にあります 。
これは、受験者の多くが合格していることを示しており、初級レベルの試験としては比較的易しいと考えられます。
試験は四肢択一式で100問出題され、制限時間は60分です。合格基準は正答率70%以上とされています。出題範囲は「ねこ検定公式ガイドBOOK初級編」から100%出題されるため、公式テキストの内容をしっかりと学習することが重要です 。
合格率が高いとはいえ、油断は禁物です。公式テキストの内容を十分に理解し、模擬問題などで練習を重ねることで、確実な合格を目指しましょう。
猫検定の合格率2024の最新データ
ねこ検定の合格率(2024年分まで) 初級:だんだん難しくなってるのか昨年は79% 中級:概ね50%前後 上級:最初は約25%だったが昨年は倍の58.5% ねこ検定に興味出た方、チャレンジ早めに! 上級躊躇してる方、中級の延長だから、初級⇨中級よりハードル低いよ! #ねこ検定合格率
2024年の猫検定の合格率は、各級で以下のように報告されています。
- 初級:約79%
- 中級:約50%前後
- 上級:約58.5%
初級は比較的高い合格率を維持していますが、中級では難易度が上がり、合格率が下がる傾向にあります。上級に関しては、過去には合格率が約25%とされていましたが、2024年には58.5%まで上昇しています。
これは、受験者の準備状況や試験内容の変化が影響している可能性があります。
なお、合格基準は全級共通で、100問中70問以上の正答が求められます。試験形式は四者択一式で、制限時間は60分です。受験料は初級が4,900円、中級が5,900円、上級が7,200円となっています。
これらのデータは、受験者が自身の準備状況を評価し、適切な級を選択する際の参考になります。特に上級を目指す場合は、過去問や公式テキストを活用し、十分な対策を講じることが重要です。
何割で合格できる?

猫検定の合格基準は、すべての級において正答率70%以上とされています。つまり、100問中70問以上の正解が必要です。
この基準は、初級・中級・上級の各レベルで共通しており、試験の難易度にかかわらず適用されます。ただし、過去の試験で正答率が著しく低かった場合、合格基準が引き下げられることもあるようです。
合格率は級によって異なります。初級は約80%、中級は約75%、上級は約25%と報告されています。これらの数値から、初級は比較的合格しやすく、上級は難易度が高いことがわかります。
試験は4択形式で、各級とも100問が出題されます。公式テキストや過去問題集を活用し、しっかりと対策を行うことが合格への近道です。
猫検定2025年はいつ?
2025年の猫検定は、3月23日(日)に実施されます。試験は全国5会場(札幌・東京・名古屋・大阪・福岡)での会場受験と、オンライン受験の2つの形式で行われます。
オンライン受験では、カメラ付きのパソコン、スマートフォン、またはタブレットが必要です。受験者は、事前に動作環境の確認を行い、試験当日に備える必要があります。
受験申込期間は、2024年8月8日(木)から2025年2月22日(土)までです。早期申込特典として、オリジナルクリアファイルや特製ノートがプレゼントされるキャンペーンも実施されています。
試験は年に一度の開催となるため、受験を検討している方は、申込期間を逃さないよう注意が必要です。詳細な情報や最新の発表は、公式サイトで随時更新されますので、定期的に確認することをおすすめします。
猫検定の合格率と難易度の関係

猫検定は初級・中級・上級の3つの階級に分かれており、それぞれで合格率と難易度に大きな違いがあります。つまり、合格率を見ることで、おおよその試験の難しさを把握することができます。
初級は合格率が非常に高く、毎年およそ80%前後を推移しています。これは猫に関する基本的な知識を問う内容で、出題範囲も公式テキスト「ねこ検定公式ガイドBOOK初級編」に限定されているため、比較的取り組みやすいレベルといえます。
猫を飼った経験がある方なら、短期間の学習でも十分に対応できる内容です。
一方、中級になると合格率は50%〜75%程度に下がります。中級では「ねこの法律とお金 増補改訂版」も出題範囲に加わり、法的な知識や猫に関する制度、社会的背景についても問われるようになります。
また、出題の一部は時事問題など公式テキスト外からも出されるため、試験の難易度は確実に上昇します。
上級に至っては、合格率が25%前後にとどまることも珍しくありません。中級に合格していなければ受験すらできないという条件付きであるため、そもそも受験者がある程度の知識を持っていることを前提にしています。
それでもなお、合格率が低いという事実は、試験内容が非常に専門的であることを物語っています。猫の医療、行動心理、さらには法律や文化に関する知識まで求められます。
こうしたデータを見る限り、猫検定の難易度は級が上がるにつれて急激に高くなる構造であることがわかります。初級は基礎知識の確認として最適ですが、上級を目指す場合は計画的に時間をかけて学習を重ねることが不可欠です。
難易度に見合った対策を立てることが、合格への第一歩となるでしょう。
猫検定の合格率から見る対策法

- 勉強時間の目安と効率的な学習
- 過去問は対策に有効?
- オンライン試験のカンニングの実態は?
- 合格すると得られる特典とは
- 猫検定を受けるメリットは?
- 猫検定は国家資格?
- 初級問題の傾向を知ろう
- 猫検定の合格率の推移と最新データまとめ
勉強時間の目安と効率的な学習
DCプランナー資格とねこ検定試験、無事に合格しました💮 次は証券外務員資格ですが、この2ヶ月勉強漬けだったので一旦休息。 ほっちゃんと菅田との時間を大切に過ごしたいと思います🥰
猫検定の勉強時間は、受験する級によって大きく異なります。初級は比較的短時間で済みますが、中級・上級は計画的な学習が求められます。
初級を受験する場合、平均的な学習時間の目安は10~15時間ほどです。毎日30分ずつ2〜3週間かけて取り組むか、週末に集中して学ぶスタイルでも対応できます。
公式テキスト「初級編」だけを使って学習すればよく、範囲も限定されているため、効率的に対策が可能です。
中級になると、学習時間の目安は60~90時間程度とされています。こちらは公式ガイドブックに加え、「ねこの法律とお金 増補改訂版」も学習範囲に含まれるため、初級よりも学習ボリュームが増加します。
また、猫に関する時事問題も出題されるため、ニュース記事や専門誌を日常的にチェックする習慣も効果的です。
上級ではさらに高度な知識が必要となり、100時間以上の学習を要することもあります。猫の生態や医療に関する内容、さらには法制度や文化の理解も問われるため、内容の深さと幅広さに対応するためには継続的な学習が不可欠です。
学習を効率よく進めるには、まず出題範囲を把握し、テキストを章ごとに分けて計画的に学習することが大切です。
重要な数字や用語、固有名詞にはマーカーを引き、繰り返し確認することも効果的です。また、音読や書き取りなど複数の感覚を使って覚える方法も記憶定着に役立ちます。
自分の生活リズムに合った学習方法を見つけ、無理のないスケジュールで継続することが、合格への近道となるでしょう。
過去問は対策に有効?
◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇ 【2024-25】ねこ検定公式厳選過去問題集 絶賛販売中!! ◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇ 第8回ねこ検定がいよいよ近づいています... 公式テキストと併せて 効率よく試験対策を行いませんか?
猫検定の過去問は、対策として非常に有効な学習手段です。特に出題傾向や問題形式に慣れるうえで、大きな効果が期待できます。
ねこ検定の問題は4者択一のマークシート形式で、100問が出題されます。形式に慣れておかないと、試験当日に緊張して実力が発揮できないケースもあります。
その点、過去問を使えば時間配分や出題のクセを体験的に理解でき、試験本番でも落ち着いて対応しやすくなります。
また、猫検定の出題は公式テキストからの出題割合が高いため、過去問と公式テキストを併用することで重要なポイントをより効率的に押さえることができます。
特に初級では、過去問から似た形式の問題が再出題されることも多く、過去問を通じて得点源を増やすことができます。
ただし、過去問だけに頼り切るのは避けるべきです。猫検定では毎年、時事問題や新たなトピックが含まれることもあります。中級・上級では出題範囲が広がり、「ねこの法律とお金」などの法制度に関する知識や、猫に関する時事ネタも問われます。
過去問はあくまで「補助教材」として活用し、あらかじめ公式テキストで基礎を固めたうえで、アウトプットの手段として繰り返し解くのが理想的です。問題を解いたあとは解説を読み込み、間違えたポイントをノートにまとめておくと、効率的に復習ができます。
このように、過去問は本試験の感覚をつかみ、自分の弱点を知るためにとても役立ちます。戦略的に取り入れることで、学習効果をより高めることができるでしょう。
オンライン試験のカンニングの実態は?
カンニングしちゃった(՞⸝⸝o̴̶̷̥᷅ ̫ o̴̶̷̥᷅⸝⸝՞)💦w でも正解嬉しいーーー😍💕 ねこはち検定一級やったーーー🥰💖💖💖 今度から身分証として使うね←怪しいやつ🤣💓
猫検定では、オンライン受験が導入されていますが、試験中の不正行為、特にカンニングに関する懸念が一部で指摘されています。
オンライン試験では、受験者の行動を監視するためにカメラを使用し、試験中の不正行為を防止しています。しかし、技術的な問題やカメラの不具合などにより、監視が十分に機能しない場合もあるようです。
例えば、試験中にカメラが起動しなくなり、画面が真っ暗になるといった事例が報告されています。このような状況では、試験システムが不正行為と判断し、受験者に警告が表示されることもあります。
また、オンライン試験の特性上、受験者が他の資料を参照することが物理的に可能であるため、カンニングのリスクが完全に排除されているわけではありません。
そのため、試験運営側は受験者に対して、試験中は他の資料を参照しないよう強く求めています。
受験者自身も、公平な試験環境を維持するために、試験中の行動に注意を払い、不正行為を行わないよう心掛けることが重要です。また、試験前には機器の動作確認を行い、カメラやインターネット接続に問題がないことを確認することが推奨されます。
猫検定のオンライン試験は、自宅で受験できる利便性がある一方で、受験者の誠実な対応が求められる試験形式です。適切な準備と心構えを持って臨むことが、円滑な受験と公正な評価につながります。
合格すると得られる特典とは
🐈第8回ねこ検定 合格特典紹介🐈 ねこ検定には、合格特典がたくさん! みなさんはいくつ知ってますか? 本日は合格者だけが購入可能な有料特典から 【合格認定バッジ】をご紹介! 初級・中級・上級でカラーが違うので、ぜひコンプリートしてください!
猫検定に合格すると、以下のような特典が用意されています。
- 合格認定バッジ:合格者には、猫検定のロゴがデザインされたバッジが贈られます。このバッジは、合格の証として多くの受験者に喜ばれています。
- 合格認定名刺:合格者専用の名刺が作成可能です。猫に関する知識を持つことを示す名刺は、猫関連の活動や仕事での信頼性向上に役立ちます。
- 特製ノート:受験者全員に、猫検定特製のノートが進呈されます。このノートは、猫検定のロゴが箔押しされたデザインで、受験勉強の記念品として人気があります。
- 特別認定証:中級・上級で満点合格を達成した受験者には、特別認定証が贈られます。これは、猫に関する深い知識と理解を持つことを証明する貴重な証書です。
これらの特典は、猫検定に合格したことを示すだけでなく、猫に関する知識を持つことを周囲にアピールする手段としても活用できます。特に、猫関連の仕事や活動に従事している方にとっては、信頼性や専門性を高める要素となるでしょう。
猫検定の合格特典は、受験者の努力を称えるとともに、猫に関する知識を社会で活かすためのサポートとなっています。これらの特典を活用し、猫とのより良い関係を築く一助としてください。
猫検定を受けるメリットは?

猫検定を受けることには、知識面だけでなく日常生活や仕事、交流の場面においてもさまざまなメリットがあります。
まず、猫についての体系的な知識を得ることができます。猫の行動、生態、歴史、文化、さらには法律や医療に至るまで、幅広い内容を学べる点は他の動物系資格にはあまり見られません。
これにより、飼い主としての理解が深まり、愛猫との関係性がより豊かになります。
次に、猫に関する仕事や活動に活かせる点も大きな魅力です。例えば、ペットショップ、猫カフェ、キャットシッター、保護団体などで働く場合、資格取得者としての信頼性や専門性が評価されやすくなります。履歴書に記載することで自己PRにもつながります。
また、資格取得を通じて自分自身の自信にもつながります。知識をしっかりと身につけたうえで猫と接することができるようになり、トラブルへの対応や健康管理にも落ち着いて取り組めるようになります。
一方で、実用面での即効性はそれほど高くはありません。公的資格ではないため、取得したからといって必ずしも仕事が増えるわけではない点には注意が必要です。
ただし、猫検定にはバッジや認定証といった合格特典が用意されており、猫好き同士の交流や話題のきっかけになることもあります。このように、知識を深めたい人にとっては非常に有意義な検定といえるでしょう。
猫検定は国家資格?
国家資格じゃないけど ねこ検定受けてみたいんだよなぁ〜 #live3
猫検定は国家資格ではなく、民間団体が運営する「民間資格」に分類されます。つまり、国や自治体が認定している資格ではなく、ねこ検定実行委員会によって独自に実施されている試験です。
そのため、法律上の資格要件として求められることはありませんし、取得によって国家資格のような法的効力が得られるわけでもありません。たとえば、獣医師や動物看護師などのような国家資格とは位置づけが異なります。
ただし、民間資格であっても猫に関する深い知識を学べる内容が含まれており、一定の信頼性や専門性を証明する手段にはなり得ます。特に、猫に関わる仕事をしている方や、猫関連の活動をしている方にとっては、自分の知識レベルを示す良い指標になります。
また、資格の信頼性は運営団体や試験の内容によっても左右されます。猫検定は2017年から継続的に実施されており、公式テキストや試験制度が整備されているため、一定の評価を受けています。
国家資格でないからといって価値がないというわけではありません。むしろ猫の知識を深めるきっかけとして、また趣味と学びを両立できるツールとして、多くの愛猫家に支持されている検定です。
初級問題の傾向を知ろう
ねこ検定初級のサービス問題の選択肢に草生えた
猫検定初級の問題は、猫に関する基礎的な知識を幅広く問う内容になっています。試験は100問出題され、すべて4択の選択式です。
出題範囲は「ねこ検定公式ガイドBOOK初級編」に完全に準拠しており、テキストの内容をしっかり理解していれば対応できる構成です。
特に出題されやすいジャンルは、「猫の生態」「猫の暮らし」「猫の歴史」「猫の文化」の4つです。
たとえば、「猫の平均体温は何度か」「猫が発情期に入る月齢」「タペタムの働き」など、数字や専門用語を問う設問が目立ちます。また、「有名な猫寺の名前」や「猫を題材にした文学作品」など、文化的な知識を試す問題も含まれます。
全体として暗記系の問題が多く、表やコラム、欄外にある補足情報まで幅広くチェックしておくことがポイントです。
たとえば、巻末のQ&Aや小見出しの中にある数字や固有名詞はそのまま出題されることがあるため、細かい部分まで目を通すようにしましょう。
また、初級とはいえ「読み飛ばしたくなるような細部」からの出題もあるため、ざっと読むだけでは得点につながりにくいのが実情です。試験対策としては、公式テキストを最低2〜3周読み込んだ上で、巻末問題や模擬試験を解き、自分の理解度を確認することが効果的です。
猫検定初級は、愛猫家であれば楽しみながら学べる内容が多く、猫と暮らすうえで役立つ知識が自然と身につく構成になっています。
日々の生活の中で猫の行動に興味を持ちながら学習を進めることで、試験対策にもつながるでしょう。
猫検定の合格率の推移と最新データまとめ

本記事では、猫検定の合格率に関する最新情報を中心に、合格の目安や試験の傾向について詳しく紹介しました。
紹介した内容をまとめたので、確認していきましょう。
- 猫検定の合格基準は全級共通で正答率70%以上
- 合格率の上昇は受験者の対策充実やテキスト改善が影響
- 初級は公式テキストから100%出題されるため得点しやすい
- 中級では法制度や時事問題も出題され難易度が上がる
- 上級は中級合格者のみが受験可能な高難度の試験
- 試験は全級とも4択形式・100問・制限時間60分
- 2026年の検定は3月22日(日)に実施予定
- 合格率が高くても油断せずにテキストを複数回復習すべき
- 合格率の上下は年ごとの出題傾向や難易度調整にも左右される
- 上級は合格率が高まっても依然として高い学習量が必要
猫の知識を深めたいけれど、資格を取るほどのレベルではない…そう思っている方はいませんか?また、「猫検定の合格率」などを調べている方の多くは、実際の難易度や勉強法が気になっているはずです。
猫検定は初級・中級・上級と段階的に難易度が上がり、合格率にも大きな差があります。初級は比較的合格しやすい一方で、中級や上級はしっかりした対策が必要です。
出題形式や勉強時間、過去問の活用法などを理解しないままでは、合格は難しくなります。
受験者の中には、猫に関する知識を深めたいという純粋な動機から始め、検定合格を通じて保護活動や猫関連の仕事に携わるようになった方もいます。
合格特典にはバッジや認定名刺などもあり、猫好きを表現するツールとしても注目されています。
もしあなたが「猫検定、ちょっと気になる」と感じているなら、次回試験に向けて今から準備を始めてみませんか?
合格率のデータを参考に、自分に合った級からチャレンジするのが一歩目です。猫との暮らしがもっと楽しく、豊かになるかもしれません。